「なぜ?」の魅力…と魔力①
幼稚園で、何年か続けて「絵画を見ながら対話をしてみよう」という活動を行なっています。そうしたら今年、珍しい現象が起きているのです。
基本的に、子ども達には自由に発言してもらっています。すると今年は「なぜ、この木は緑で描いたんですか?」といった、「なぜ」質問がとても多いのです。
こちらとしては、「ここにアパートみたいなのがある」とか「この人は怒っていると思う」的な発見を期待しているのですが、「絵を見て、気づいたことの“なぜ”を問いたい」子が多いのですね。
それこそ「なぜ、この子たちはこんなにも、“なぜ質問”をしたいのだろうか?」と不思議に思いました。ちなみに、子どもが「何故?」と聞いても、私(進行役)は答えません。「◯○君は、これがどうしてか?何故か?を知りたいんだね」と、本人の疑問文をオウム返しするだけです。

…それって、盛り上がらない気がするけれど。
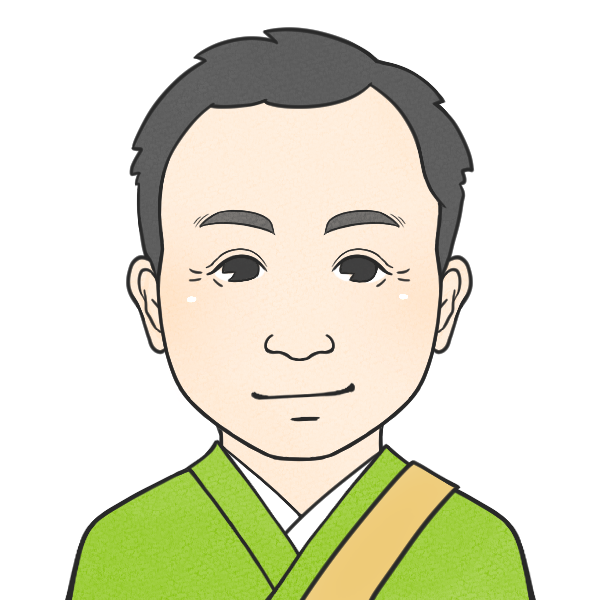
そうなんです。盛り上がらない。けれど誰かが「なぜ?」という発言をすると、芋づる式のように「なぜ?」が出てくるんです。ときおり、「さっき、◯○ちゃんが聞いていたのは、△△だからだと思う」という意見は出るのですが(立派なものです)。…
ここからは想像ですけれど、子ども達は普段よっぽど沢山の「なぜ?」に晒されているのではないだろうか。それが科学的な問い…「なぜ、この花びらは4枚なんだろう」であればいいのですが、「あなた、なぜこんなことしたの!」という問われる側…であったら、辛いだろうな、と。
自分の普段の生活を思い出しても、「なぜ?」と問われる時は、だいたい旗印が悪い時(笑)です。「何で知らせてくれなかったの?電話一本くらいできるでしょう」みたいな。

アッサリ謝らせてくれないんだ…
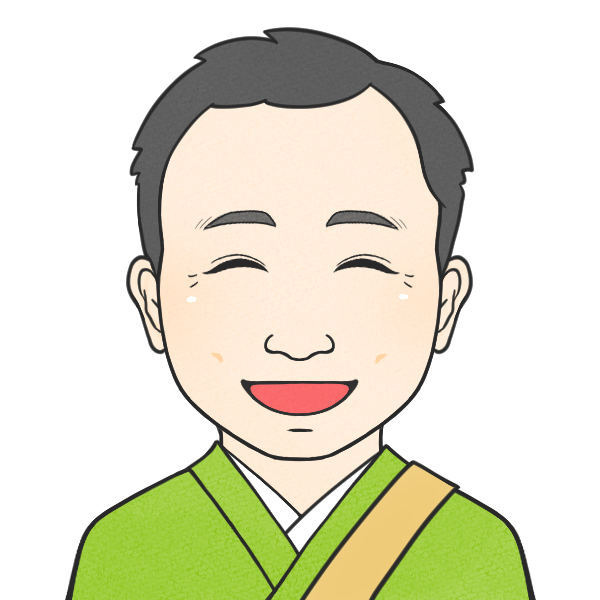
でも、それを問い詰めている本人も、おそらく過去、誰かに詰められて窮したことがある。これが有効な問いだと知っている。だから使うのでしょう。
有効、とはこの場合、どんなメリットでしょうか。それは自尊心かもしれません…「僕の寂しかった思いを埋めてよ!」という願いなのかも。

仏教の基本的態度
仏教は、何かを一方的に教え込むよりも、自らを問い直すことで成長していく道を重んじます。釈尊も、多くの場合“答え”を与えるより“問い返す”ことで、弟子や在家信者の心を開きました(対機説法)。
問いは、相手を育てることもあれば、追い詰めてしまうこともあります。
皆さんは「なぜ?」と聞くとき、どんな気持ちで言っていますか。
続く。

