写真の衝撃
何だか「アートの歴史」みたいになってきました(いずれは宗教論になります)けれど、「写真の登場」はアートにとって相当な衝撃だったはずです。そもそもアート作品は、「如何に本物と似せた描写をするか」が大切だったわけで、「上手な絵」というのは基本的に「似ている絵」であったはずです(逆に、記号としての絵は文字に進化していったと思われます)。その役目をカメラに、フイルムに、写真に取って代わられた。さまざまな技法も写真一枚に収まってしまう。明治でしたか、「写真を撮ると、魂を抜かれる」という考えが出たそうですが、「鏡をご神体とする」日本の歴史からすると、素直にうなずけるものです。
さて写真というものが世に出て以来、画家さんとか作家さんは相当な危機意識を抱いたはずです。「記念日には家族の肖像画を」だったのが「写真を」になってしまうのですから。「我々のやっていることに、どんな意味や価値があるのか?」を突きつけられたはず。
もちろん、当時はさまざまな「科学技術」が押し寄せて、似たような問題は広範囲におきていたはずです。仏教界でも「科学的な」知見と齟齬のないあり方を模索したはずです(今の「明るく・正しく・仲良く」という言い方は、この頃に生じたようです)。
そんな状況にあって、「写真にできなくて絵画にできるもの」を模索したのは当然の反応でしょう。一つは「本物、のないもの」。つまり言葉でしか表現されていないものの可視化です。昔話の「川で洗濯をしていると、大きな桃が流れてきました」の絵は「本物に似ている」という評価に馴染みません。次に「抽象的なもの」。喜び、とか恐れとか、あるいは偶然の産物とか。これは言葉としても共有されない(されたとしても、ボンヤリとしか)もの。「嬉しそうな顔」は具体的に描けても、「喜び」は抽象画となりますね。そしてもう一つが「対象を、自分なりに捉えたもの」。印象派とかは、きっとここにあたりますね。これら3つはいずれも客観性が低く、主観的な活動ということができます。この主観性をもってアートと定義しなおすことになったのが、写真の出現による変化だと思うのです。「アーティフィシャル」は「人工的」と訳されますが、機械とか冷たいイメージではなく、シンプルに「人の目をとおしたもの」という意味なんだろうと思います。
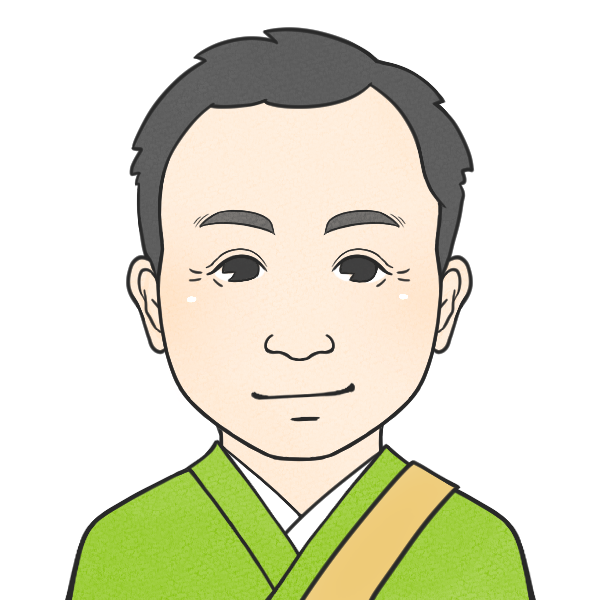
どうでしょう?私の解釈は、昨日の古今和歌集に引っ張られすぎているでしょうか…?

