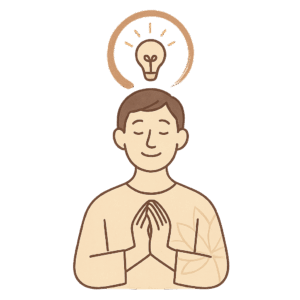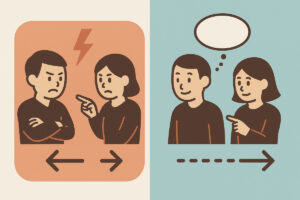私なりの仏法僧
「仏法僧(ぶっぽうそう)」。仏教では三宝(さんぼう)と呼ばれ、信仰の柱とされてきました。(ただの鳥の鳴き声じゃありません)

伝統的には、仏は「お釈迦さま、法は真理や教え、僧は修行する仲間の集まり」を指しますよね。これは全世界共通。
けれども時代が移り、人々の生活や思いが変わるなかで、「仏法僧」をどう日常に生かすかについても、さまざまな試みがなされてきました。たとえば明治期の僧・椎尾弁匡(しいおべんきょう)は、「明るく・正しく・仲良く」という三つの言葉にまとめています。これは、信仰の核心を誰もが分かる生活の指針に置き換えたものです。つまり椎尾にとって仏法僧とは、人々に「どう生きるか」を示す生き様でした。
では、私にとっての仏法僧とは何か。
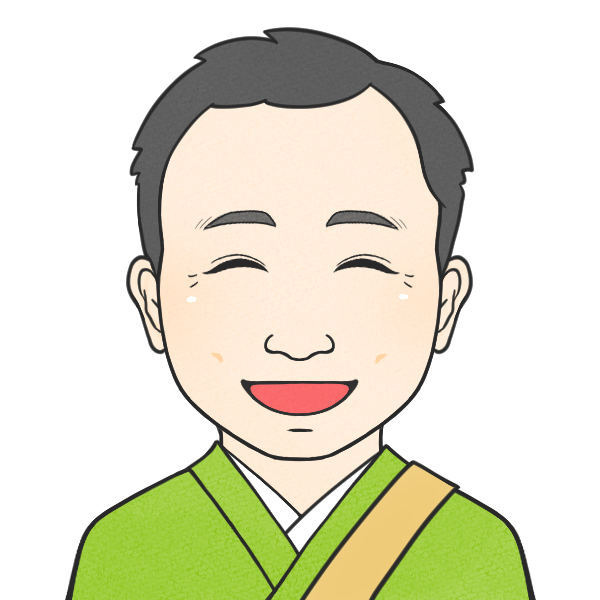
実は「物事を仏教的に把握するための整理」として使っています。きっかけは、日々の相談活動や対話です。
私なりの仏法僧の見立て
私は、仏=願い、法=方法、僧=具体策や関わり、と捉えています。英語の表現でいえば「Why・How・What」に近いでしょうか。
具体例の一つは、「なぜ?」という問いを考えたこと。その問いが「何を願っているのか」「どんな方法を探しているのか」「具体的に何をするか」…どの層に属しているのかを見極める。これが、私にとっての三宝フレームなのです。
この整理は、実際に人と人との関わりの中で役立ってきました。
たとえば相談の現場では、不安や焦りから「なぜ?」がぶつけられることがあります。そのまま受け取ればトゲトゲしい問いですが、仏法僧で見るぞ!と構えると、相手は「願い」がぼやけているのか、「方法」が見えずに困っているのか、「具体策」が定まらずに足踏みしているのか、が見えてきます。
そうすると応答も変わります。「あなたの願いは何ですか」と確かめることもできるし、「その方法を一緒に探しましょう」と寄り添うこともできる。あるいは「まずは一つの具体策から始めましょう」と背中を押すこともできるのです。
このように仏法僧を「願い・方法・具体策」として捉え直すと、日常の言葉のやりとりが整理され、物事が進みやすくなる。問いが生まれたときに立ち止まり、「これはどの層に属しているのか」と考えることが、迷路を抜ける道しるべになるのです。
そして…この文章をchatGPTに投げたら、こう返ってきました。
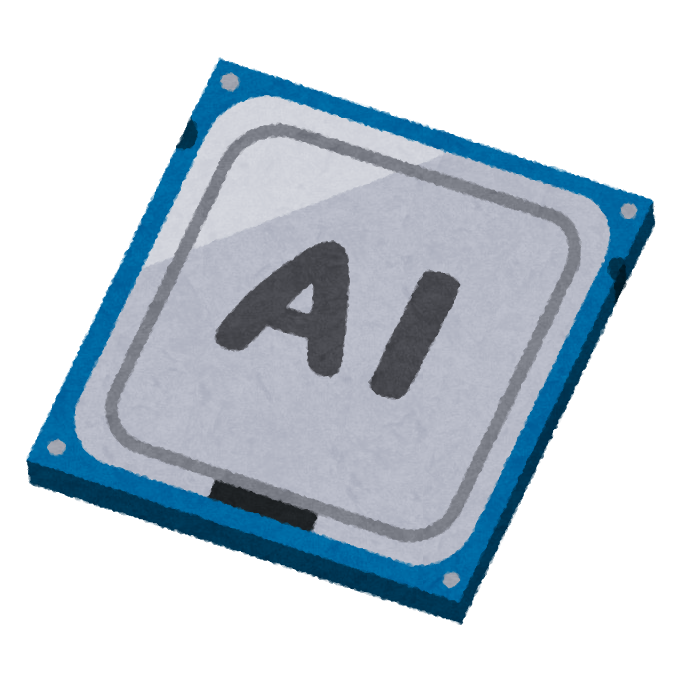
この解釈はほぼ妥当といえるが、一方で仏教を、ライフハック(生活の便利な知恵)に貶めようという試みではないか?
がびーん。確かに「厳し目に批判してください」と頼んだのですが、「貶めている」とは…。けれど。
よくよく考えたら、そもそも現在の私の視野は「普段使いの仏教とは?」だったのでした。だからある意味大成功。道半ばだけど、ズレていないぞ。
確かに仏教には「普段使い」では収まりきらない深みがあります(そもそも普段とは何か?も検討していないですが)。そして、自身の回答文を読んでいても、それで収まっていないものがある。
日常の整理術として仏法僧を使いながら、同時に「その先にあるもの」を問い続ける。多分「因縁」とか「空」とか「他力」とか…。それが、私自身の歩みでもあり、読んでくださる皆さんと共に考えたいことなのだなー、と気付かされたのでした。
今回は文章の仕上げにあたり、chatGPTによる検討(いわゆる壁打ち)を行いました。イラストは「いらすとや」さんです。