「悪縁を絶つ」かぁ…
他人の相談に乗っていると、いつの間にか自分と向き合い、自分の考えていることが言語化されることがあります。
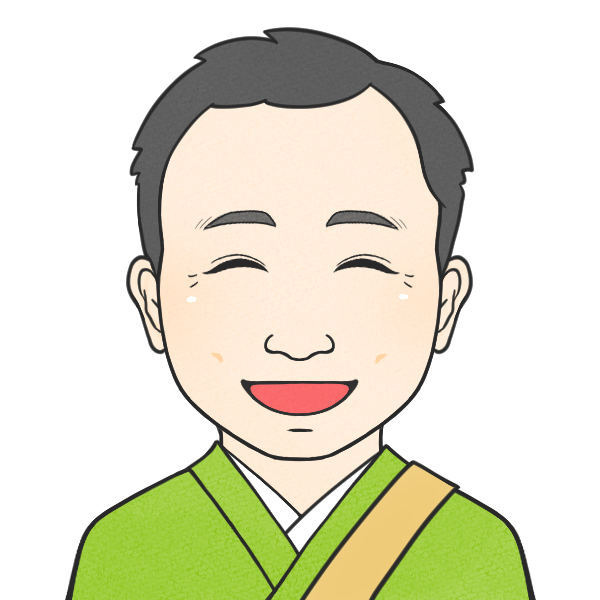
またもや「お坊さんに相談しよう」サイトからの引用となりますが、自身の浄土宗僧侶としての一定の到達点のような気がしますので、ぜひお伝えしたいと考えました。(一部改変)
(要約)「努力しても何度も家族や周囲から足を引っ張られ、まるで“得体の知れない力”に苦しめられているようだ」と感じる。
hasunoha 回向と悪縁切りについて
周囲からは「それは先祖の悪行が原因で、因縁が祟っている」「悪縁を断ち切りなさい」と言われ、どうすれば“地獄のような繰り返し”から抜け出せるか知りたいというお尋ねでした。この方はまじめに祖母の介護を続けてきたにもかかわらず、親族の不和や孤立の中で心身ともに疲弊し、「自分が何のために生きているのか分からない」と感じておられます。
「因縁」「回向」「悪縁切り」という言葉をどう理解し、どのように実践に結びつければいいのか…その整理を求めておられました。
仏教的整理…因縁・回向・悪縁切りについて
◎まず「因縁」とは、すべての出来事を成り立たせている関係のしくみを指します。そこに善悪の判断はなく、「何がどう関わってこうなっているのか」を観るための言葉です。
◎次に「回向(えこう)」について。
この捉え方は大乗仏教の特質(自業自得ではなく、言わば自業他得)です。回向の本来の意味は「自分の善い行いを、他者の幸せのために振り向ける」ことです。例えば阿弥陀仏は、自らの修行の功徳をすべての衆生の極楽往生に回し向けました。「善い行いを」であることが回向を成り立たせます。
◎では、これらがなぜ、「悪縁切り」という話に繋がるのでしょう。
まず、「因縁」を「悪縁」と混同してしまうと、(言わば淡々と生起している)仕組みに悪という価値観を付けることで、原因を切り離すことばかりに意識が向き、苦しみの構造を見直す機会を失ってしまいます。悪縁を「断つ」よりも、因縁を「観る」ことが、仏教的な歩みの第一歩です。自分の苦しみに繋がっている縁がどれなのか?を観ずして「どの縁の作用によるものか?」が解ろうはずもありませんよね。
次に回向について。「回向」の誤用があると、あなたが聞かされたような無茶な話になります。自業他得という文脈(後半)に悪行を載せると、「先祖の悪行が〜以下略」が完成です。
私達が住んでいる娑婆世界は、基本的に自業自得の世界です。そうであれば「先祖が悪行をしたならば、本人がその結果を受け取る」はず。いま自分が苦しんでいる仕組みは…百歩譲っても「自分が前世で悪行を行ったから」までです。
だから「先祖の悪行が子孫を苦しめてる」は、仏教の教えからは二重に間違っているのです。
ではどうすれば…?
それぞれの言葉の意味(や限定)を含めた理解をし、行動することです。
私たちがご供養を行うとき、それは坊さんのパワーが不思議な力を発揮しているのではなく、仏さまの慈悲(他力)を通じてご先祖に回向されているのです。ですから、たとえ先祖がどんな過ちを犯していたとしても、あなたが阿弥陀さまに願いを向けるかぎり、回向は正しい方向に働きます。
南無阿弥陀仏と口に称えることは、「阿弥陀様、あなたのお力でご先祖様をどうか導いてください」と願うことの表れ。私達に、それ以上できることがあるでしょうか?
日々の具体的な行動として
難しく考える必要はありません。先ほどのお念仏に加えて、仏前に手を合わせ、祖母やご先祖に「私は今日も生きています」と事実を報告する。それで十分です。「得体の知れない力」が頭をよぎったら、「仏さま、私には対応しきれないのでお願いします。私は私のできることをやります」と分担しましょう。
…本来は「公共窓口などに繋がろう」「まず心身を意識的にでも休ませよう」も回答すべきなのですが、文字制限で断念しました…
さまざまな「迷信・曲解」からの自由
今回の質問では、特に「回向」と「得体の知れない力」について訊ねたい様子でした。因縁という言葉は「善因善果・悪因悪果」とも言われ、「先祖の悪果が縁となって現前の私を苦しめる」という意味の「悪縁」にも繋がりやすい。「縁切り寺」というのもあります(これは、酷い旦那から妻が逃げるといった文脈の、現前の縁を物理的に切るというのが発祥です)。
その辺りは、歴史の中で様々な苦と向き合う中でバリエーションが増えた結果とも言えます。ただ多分本流は「因縁や回向という言葉について、正しく知る」ということに尽きるかと思います。特に現代は「自己責任」がワーワー言われますから、「回向」というのは「無駄」あるいは「ちょっとした美談」とかに絡め取られがち。大乗仏教における非常に重要な論点なのにー。
様々な思考の展開は可能と思うけれど、最終的に「生きる苦に対処する」に繋がらなければならない。一つの考え方が万人に(どんな状態でも)受け入れられる訳でもない。やっぱり発信(因)と受けとめ(縁)によって、結果は出るのです、ねぇ…。
※ 今回は、「質問文の要約」と「回答作成に至る思考の整理と評価」で、AIを利用しました。最後の囲みまとめが、やたら人間くさい語尾になっているのは、AI疲れかも。

