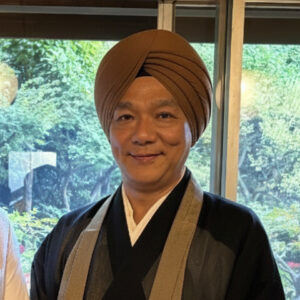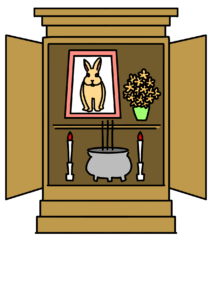AIに相談しよう!
AIは信頼されているらしい。
イヤ、相談を勧めているわけではないのです。
先日、こんな記事を目にしました。
… 対話型AIは「親友」「母」をわずかながらも上回り、対話型AIが最も「感情を共有できる相手」に選ばれていることが調査結果で明らかになった。(中略)
忙しい日常の中で、家族や友人に相談する時間が取れないときも、AIは常に受け入れてくれる。しかも否定されない、急かされない、怒られない。まさに現代人にとって理想的な安心感を提供してくれる相手だろう。
そう言えば、私が十年来活動している「hasunoha」という「お坊さんに相談しよう」サイトでも、AI僧侶というのが登場して数年が経ち、今や「人間のお坊さんよりも多くの質問を受けている」というのです。
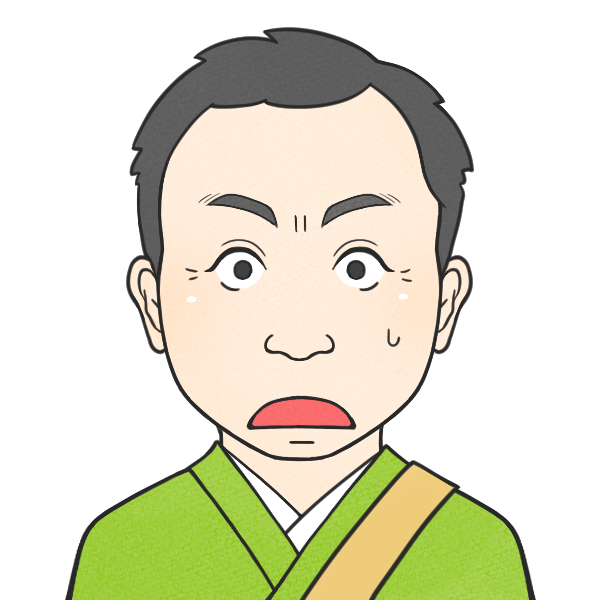
何となくショック…だけれど、予想されたことではあるな。
確かに、オンラインが舞台である以上、回答はデータとして蓄積されていくし、仏教の理論自体はそう変わるものではないので、AIが答える、というのはある意味適任なのかも知れません。先ほどの記事で指摘された「いつでも・いつまででも・否定されず・怒られない」というのは、相談者という立場から見れば「理想的」というのも分かります…相談の現場にいるので。

そう言えば、「AIでミニ良文を作ってみたい」とかもあったね。今は頓挫しているみたいだけれど。
ああ…「AI位牌」とか「AI遺影」みたいな、ね。「それに問いかけると、あたかも本人が居るかのような受け答えをしてくれるフォトスタンド」的な。結構トレーニングして「自分らしい回答をするようになった、かな?」と思ったら、全然ピンと来なかったので。どうも「学習」というのは抽象化・一般化のことであって、人間の個性は再現できないみたい(今のところ)。

完成したらそれは…究極の「推し活」グッズだね。

レポート作成にAI利用…
実は、この「手軽さ重視」、社会全般に及んでいる気がします。
代表例は、「大学のレポート作成に、生成AIを使うことの是非」についての言及。基本的スタンスは「禁止と明示されていなければ構わないが、参考に止めよ」ということのようです(今のところ)。
まぁ想像でしかありませんが、「手軽に得た結論は、軽い」ですから、「AIに書いてもらったレポートの内容は本人に定着しない(学びにならない)」のは当然でしょう。文章って、何度も推敲して読み返すから身につくんですよね。私自身の「回答」を読むと、どんな問いだったか思い出せることは多いですもの。この辺りは「粘り強さ」という非認知的能力の育成が、AIの登場によって阻害されるという話になりそうです。
そしてまた、受け手にとっても馬鹿馬鹿しい感じがしそうです。「AIが書いた文章を読まされる、先生という仕事」って(むしろ事実確認とか、小論文の採点をAIに手伝わせるのはアリかも、と思う)。
今後、心配なこと
子どもに対しては、親が端末のコントロールをすることができます。けれど、大人がAIに相談すること、自体は止められないと思うのです。なので大切なのはリテラシー。使うにあたっての留意事項です。
私が今のところ考えていることは下記4点です。
①子どもや学生にとっては、「レポートとか宿題とかは、その内容そのものより重要なのことがある。それはプロセスや体験だ」と知ること。将来家庭を持って「お前、これどうすんだ!」と言われた時に「chatGPTに聞くから、ちょっと待って」とは言えませんからね。…優先順位を知っていてね、ということ。
②大人にとっては「最後に自署できる提出物を作ろうよ」ということ。参考にしたり壁打ちしたり仕上げチェックしてもらっても構わない。けれど最後に「By わたし」と書けるかどうか。
③AI相手の相談だと、「ガチャ化」しそうな気がします。実際、「気に入らない回答は受け付けない人」は結構います。自分が気にいる回答が来るまで質問を続ける…というのは「行動に移せない」という意味で良くないな、と。それが手軽に実現されそうで、イヤな感じがしています。データセンターだってイヤだろうよ、「またこれ聞いてきやがった」って(笑)。
④相談とか人生においては、「身体性」が最後には必要なこと。どれだけAIとの質問を重ねても、彼が「疲れた」と言うことはないけれど、こちらは「お腹へった」「トイレに行きたい」「眠い」となる。無言になる時間もある。その違い…を無視しないこと。お寺の玄関口で、対面しながら相談していると、文字より遥かに多くのことを感じるのです。疲れた感じや困っている表情。質問しながら自分で整理している雰囲気。そういった「デジタルが掬えない部分」に、人間の喜びってあるような気がします。「ちょっと、一息入れようよ。お茶いれるから、待ってて。」そういう場を、大切にしなければ。
ひとまずのまとめ
今回の「AIの波」は、会話ができるということと、解答に方針が与えられていることが特徴だと思います。闇雲に学習するのではない。けれどそれは、人間の様々な可能性の中、「有用と思われる特質」だけを抽出したもの。「決して否定しない」は御尤も(ごもっとも)と思うけれど、それは「絵に描いた餅だから良いのでは?」とも思うのです。なぜなら人間には身体があるから。情報化できる事だけに触れていると、人間の瑞々しさとかが退化していきそうで、心配なのです。
随分と語りすぎました。しかしいずれ、またこの件考えます。