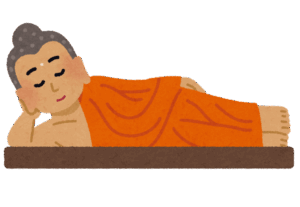「なぜ?」の魅力…と魔力②
今回は「なぜ」を人間関係に使う、プラスとして使える縁(条件)を考えてみようと思います。
前回は、いきなり「なぜの魔力」の方を書いてしまいましたので(笑)。
ふだん私は、人に向ける「なぜ?」は会話を閉じやすいと考えています。特に問題の起きている時。「なぜ?」という質問は相手を理由の弁明に引きずり込み、「取りあえず、この場をおさめなければ」という新しい課題を生み、結果として事実が見えなくなるからです。

ビジネスでは「問題が起きたら、なぜ?それはなぜ?それはなぜ?と三段深めよ」といった言葉もあるようだけれど、日常会話でそれは辛すぎる。
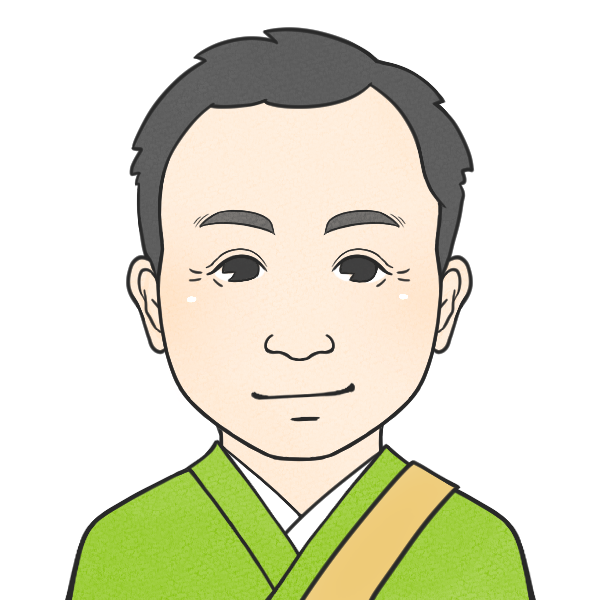
ですよね。ではいったい、どのような縁(条件)が整えば、「なぜ?」は人を支え、願いを見つける灯になるでしょうか。今日はその“効く場面”を、仏教の視点から整理してみます。
- 1.肯定に向ける「なぜ?」――喜びの源を深める
失敗の理由ではなく、うまくいった出来事に「なぜ?」を向けると、相手は安心して語れます。
「今日は、なぜうまく進んだのでしょう?」と尋ねると、準備・偶然・支え手といった因縁(良縁)が掘り出されます。原因の構成が見えると、再現の見取り図が描けます。結果だけを褒め合うより、次の一歩が進めやすくなります。
- 2.自発に向ける「なぜ?」――“自分ごと”を取り戻す
外からの評価ではなく、自分で選んだ理由を確かめる問いです。「あなたにとって、なぜそれを続けたいのですか?」――この問いは、正解を求めません。心の中の“納得”を呼び起こすのです。誰かに説明するための理由ではなく、原点や自分が歩き出せる理由を思い出すことで、足取りが軽くなります。
- 3.願いを映す「なぜ?」――大切にしている価値を浮かび上がらせる
仏教の「仏法僧」でいう「仏」は、私たちの内にある願いとも言えます。
「なぜそれが大事だと感じるのでしょう?」と問うと、背景にある価値感(願い)が姿を現します。願いが見えると、次に選ぶべき法(道理・道筋)も見えやすい。問いは責める道具ではなく、「願いの輪郭」を描く鉛筆になります。

- 4.学び直す「なぜ?」――過去を責めず、意味づける
同じ「なぜ」でも、責任追及ではなく学びの整理として使うこともできます。
「あの時は、なぜ別の選択を取りにくかったのでしょう?」
状況・感情・制約という因縁を丁寧に並べると、自己否定ではなく理解へ向かいます。「ああ、こうだったから、あの時の選択しはこれだったんだ」という理解。理解があると外在化されやすいので、検討や反省はしやすいですが、後悔に沈みません。理解が次の行動を静かに後押しします。ただ、このときも聞く側は仏法僧を心掛けるべきです。「誰が悪いという前提ではなく、これが起きた仕組みを一緒に理解しましょう」というスタンス。「どんな結果をもたらしたいのか」という願い(仏)が通った会話を心掛けましょう。
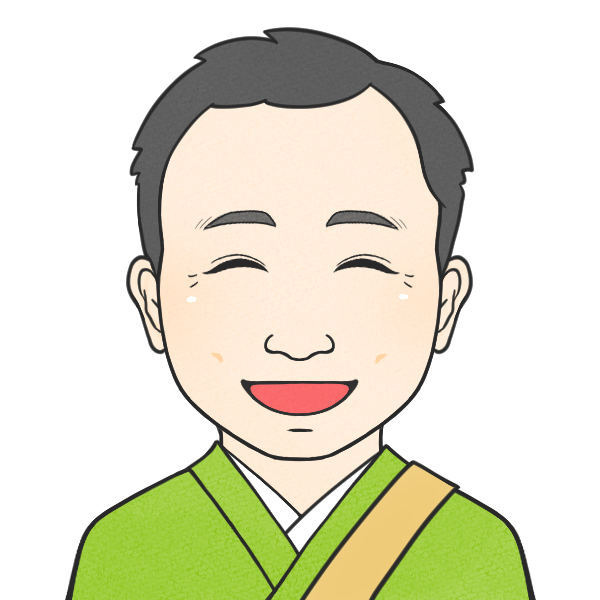
これは…なかなか難しいかも知れませんね。ついつい瞬時に「相手を責めよう、謝らせよう」という目的を持ちがちですから。相手と共に「問題の構造を見極めよう」という姿勢を、思い出せるようにしたいものです。
普段(あるいは印象的に)使われる「なぜ?」は、責める場面が多いと思います、正直。ですから、前置きとして「責めるのではないよ」「言いたくなければ、ゆっくり考えてからでいいよ」「一緒に紐解いていこう」といった言葉も必要なのだろうと思います。けれど上手く使えれば「何を願っているのか(仏)」「どのように行えばより良いのか(法)」「何をしたら良いのか(僧)」を掘り出せる言葉。
うまい「なぜ」の使い手になりたいものです。