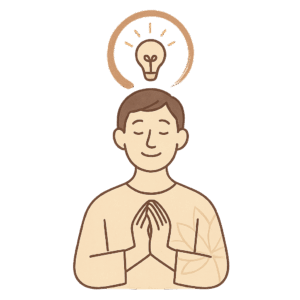形あるものは壊れる…それでも残したい銀杏の木
今年は戦後80年ということで、太平洋戦争(第2次世界大戦)がらみの事を多く目にします…報道されています。そして、光円寺としても2紙(東京新聞・読売新聞)の取材を受けました。前者はお檀家さんがご連絡くださり、紙面をお届け下さいました。
後者は今日(18日)、取材に来ています…暑い中お疲れ様です。よほど大きな事件がなければ、20日の朝刊に載るだろうとのこと。
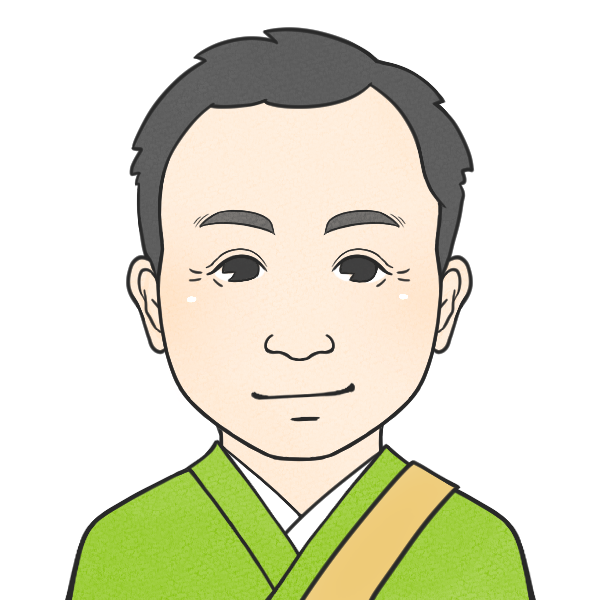
取材のテーマは、「光円寺の大銀杏…戦災の記憶を伝える」といったところのようです。東京新聞は芸術家さんが絡んで変化球になっていますけれど。
今年のお施餓鬼会でも「銀杏の木の今後が心配」とお話しましたが、にわかに大銀杏がメディアに露出しているのです。多くの方が関心を寄せてくれるのは、基本的にはありがたいことです。

いちょう寺の銀杏に関心を寄せる方があるならば、それに答えるのも公共的使命では?
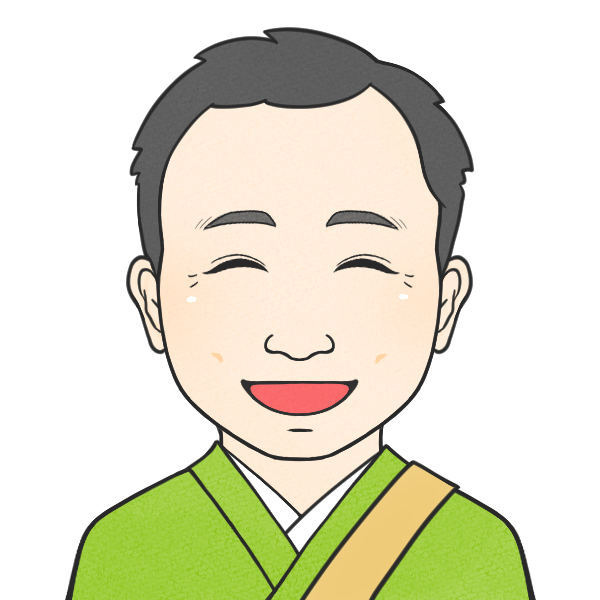
確かに…その通りです。でも一筋縄でもないんです。
いやー、歯切れが悪いったらないですね。ただ…多くの人が目にするということは、それだけリスク・危険度も増すということ。すでに傷つけられた歴史がありますから、単純に喜んでではいられないのです。

今年、これだけ取材されるきっかけは、令和5年に刊行された『甦る戦災樹木』でしょう。著者の菅野氏が様々なメディアにお声がけくださったのだろうと推測しています。恐らく10年以上かけて、東京中は言うに及ばず全国の戦災樹木を取材して来られました。その努力には頭が下がります。
さてさて一方、住職という立場で、この木に(あるいは現象に)どのように関わっていけば良いのか?付き合っていけば良いのか?は、なかなか難しい問題と感じます。
①巨木?…分かりやすいけれど、観光地じゃあるまいし、痛んだりイタズラの心配もある。
②戦災樹木?…現代史の生き証人としての意義は認めるけれど、浄土宗とか仏教とは関係ない。
③信仰の対象?…仏様ではないので、信仰の対象ではない。生命力とか迫力は感じるが、同時に「死にゆく存在である」ことも分かる。
現時点での私という視点から見た銀杏の木
少なくとも「いちょう寺」と呼ばれ、何百年もの間、多くの人が守ってきた木なのだから、徒に傷つけることなく、次代へ繋いでいきたい。日本の歴史と共に、非常に多くの人たちが見上げてきた…逆に言えば人たちを見送ってきた存在であり、人間の寿命に比べれば遙かに長い時間を生きてきたわけだから、敬意を持って接するべきだと思う。それはひとり私ではなく、関わる人全てに強いたいほどである。
そのために、どうしたら良いのか?
情報を集めようとすると、すでに6年前(2019)年には「保全・保護制度の確立」に向けた提案がされているものの、私がそれ自体を初めて見つけたのが今回(6年後)というのが現状です。ここには「所有者・管理者が適切な管理方法を熟知していることも期待できず」とあって…イヤその通りですが、どうするの?「ずっと立っていて欲しい」と願うだけではダメでしょうし、「形あるものは全て壊れるのです、南無阿弥陀仏」と言ってアッサリ引き下がれるものでもありません。幸い、お檀家さんに紹介いただいた「樹木医」さんからは、「当面いまの対処で大丈夫でしょう」と言われて一安心しているのですが…。この先、再び震災に遭わないとも限りませんし。

まずは近くの先輩のお寺とか、木の種類は違っても地元で連絡会みたいなのを作ってみては?
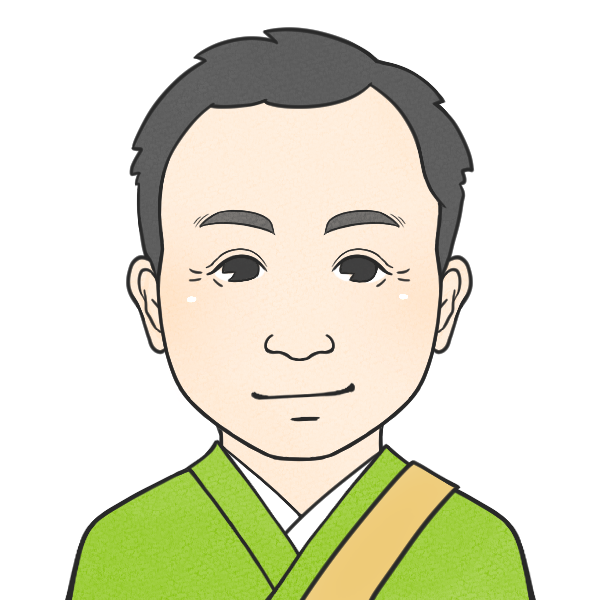
そうですね、そこで保存状況とか話し合う。あとは「どのような形で残していくか」について、智慧を出し合いたい。単純な話としては「看板の設置」とか、「写生大会・撮影大会」とか。「幼稚園の奥にあるがゆえ、気軽に入れない・近づけない」ことをメリットとしていかねば。