怒りは願いの裏返し
お坊さんへの質問サイトで、印象に残る相談を目にしました。
内容はこうです。
「信頼していた相談員に裏切られた。事実をもみ消され、自分も解雇された。今は生活も安定し、恵まれた環境にいるが、それでもその人のことが許せない。どうすれば忘れられるか?」
感情が揺さぶられるエピソードでした。
相談者の怒りは正当なもののように思われ、しかもその怒りが日常生活をじわじわと侵食している様子が、行間から伝わってきます。
仏教では、怒りの感情そのものを否定しません。むしろ、「怒りとは、大切なものを傷つけられたときに生まれる、心からの反応」として、正面から見つめようとします。
そして、さらに一歩踏み込んで考えるのです。
たとえば、『摂大乗論(しょうだいじょうろん)』という仏教書には、こんな趣旨の言葉があります。
「感情は、智慧と方便によって変容させることができる」と。
つまり、怒りという激しい感情も、智慧(物事を正しく見る力)と方便(相手に合わせたふるまい)によって、柔らかく、力強く、他者と自分の助けになる形に変えることができる――と説くのです。
もう少し分かりやすく言えば、
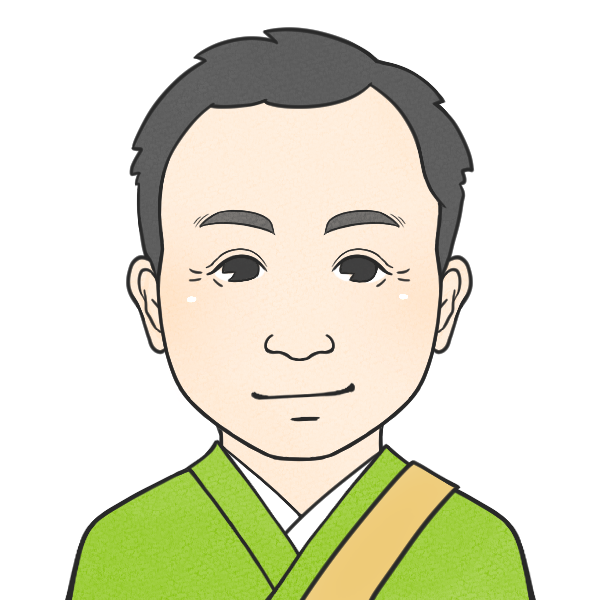
怒りは「願い」の裏返しなのです。
「裏切られたくない」という願い。
「人として誠実でありたい」という願い。
「正しいことを大切にしてほしい」という願い。
それが裏切られた時、怒りが湧いてくる。「失ったとき、その大切さに気づく」ようなものです。
だからこそ、その怒りの力を、相手に向けることから自分自身の「方向性」に変換していくことが、仏教の目指す道なのです。
具体的には、こういうことです。
「私はあんな裏切りはしない。だからこそ、誠実に生きよう。」
「誰かが苦しんでいる時、私は見て見ぬふりをしない。」
「許せない、と思うその感情を、私の願いの証にしよう。」
これは簡単ではありません。とてもエネルギーのいることです。
「怒りは沈めようとしても、消えないことがある」のであるならば、怒りを変換することで、超えていくという発想の転換です。
仏教では、怒りを三毒(貪・瞋・痴)のひとつとして扱いますが、それは怒りそのものを悪とするためではありません。「扱い方を間違えると、自分をも壊してしまう」という智慧の表現なのです。
実際、今回の相談者も「忘れよう」としているように見えて、(多分)心のなかではその怒りを育ててしまっている。
そうならないためには、「具体的行動」が必要です。

このように、「私の願いは、こういうものだった」と明らかにし、それを言葉や行動で表していくことが、怒りの沈静化にはとても効果的なのです。
たとえば――
・「私はどう生きたいのか」を改めて紙に書き出してみる
・「怒りがこみ上げた時は、南無阿弥陀仏と称える」
・「信頼できる友人に、自分の“願い”を話してみる」
仏教は、現実の感情や苦しみの中にこそ、救いの入り口を見いだします。あなたの中の怒りが、あなたの願いとつながったとき、それはきっとあなた自身を強く優しくしてくれるでしょう。
今日の一つの問いが、どなたかの日常の支えになりますように。

