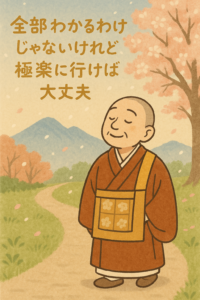山口周『世界のエリートは、なぜ美意識を鍛えるのか』を読んで――瞑想と美意識、ふたつの“観る”実践
ビジネス書でありながら、どこか仏教と通じるような本でした。山口周さんの『世界のエリートは、なぜ美意識を鍛えるのか』は、データや論理だけでは立ちゆかない時代において、「直感」や「美意識」がいかに意思決定に影響を与えるかを説いています。
分析や合理性は、もはや誰もが使える“サイエンス”としてコモディティ化している──だからこそ、人間の「意味への欲求」や「世界観で選ぶ態度」が差を生む。山口氏はそれを「ファッション化」と呼びます。決して否定的な意味ではなく、機能や価格以上に、物事の背後にある「意味」や「物語」に人が惹かれる現象を指しています。
この本を読みながら、私は仏教の「観察(ヴィパッサナー)」の実践を思い出していました。お釈迦さまは悟りに至る過程で、何かを学んだのではなく、ただ静かに呼吸を観、身体の感覚を観、心の動きを観ていました。そこには「正しい答え」を求める姿勢ではなく、「あるがままを観る」という姿勢が貫かれていたように思います。
山口氏が提唱する「美意識を鍛える行動」もまた、同じように“観る”ことから始まります。たとえば、美術館に行ってアートを観る。とはいえ、こんな経験はありませんか? 絵画の前に立っても、ついついキャプション(説明文)ばかり読んでしまう。「これは誰の作品か」「どういう意味があるのか」──私たちはつい、すぐに“理解”しようとしてしまうのです。
けれど本来、アートには正解がありません。自分が何を感じるのか、自分の中で何が動くのか。それを“感じ取る力”こそが、美意識の鍛錬であると山口氏は言います(多分)。それはまさに、仏教における「観る」という修行そのものです。意味を先に探すのではなく、意味になる前の“ただそこにあるもの”を見つめる。仏教ではそれを「観(かん)」と呼びます。
この“意味の前にとどまる”態度は、忙しく答えを出すことが求められる現代では、むしろ鍛えなおす必要があるのかもしれません。合理性や効率に慣れた私たちにとって、「ただ観る」という行為は、意外なほど難しい。でもその分、そこから得られる気づきは深いものです。
また、山口氏の言う「ファッション化」は、仏教の儀礼や仏具、作法の背後にある“意味”を読み取る営みにも重なります。形の奥にあるものを感じ取れるかどうか。そこに、私たちが文化や宗教を“自分のもの”として生きるヒントがあるように思います。
山口氏が語る「美意識」は、仏教でいうところの「観察力」や「直観知」に近いと私は感じました。何かを決めつけず、分類せず、ただ見る。そしてその見ることを通じて、自分の中に育ってくる“何か”を大切にする。それは固定的な「悟り」や「答え」と呼ばれるようなものではなく、日々を少しずつ深めてくれる感覚かもしれません。
忙しさや情報に埋もれがちな毎日ですが、ほんの少しだけでも「観る時間」を持ってみませんか。美術館の一枚の絵でも、夕焼けの空でも、子どもの寝顔でもいいのです。その時間が、私たちの心を柔らかくし、答えのない問いに向き合う力となってくれるはずです。
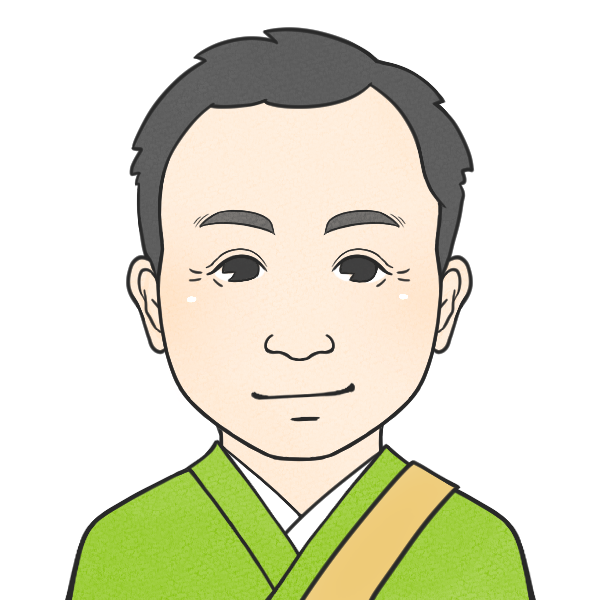
今回は、chatGPTと相当やり取りしながら作成してみました。イイタイコトから始まり、提案を受けたり検討したり。「もっと〜して」もたくさん。最近では、違うテーマで対話していることも絡めて提案してきたりして、「お主、分かってきたな」と感じる事も多くなりました。